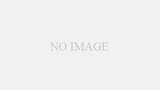日本にシャーマンは存在するのでしょうか?もし存在するなら、どのような人々を指すのでしょうか?
まずは「日本におけるシャーマンとは何か?」を考察し、
次に「日本各地のシャーマンたち」を紹介していきます。
この記事を読み終える頃には、日本にいるシャーマンについて理解できるでしょう。
日本のシャーマン・巫女について
日本におけるシャーマンを理解するために、まず「巫(かんなぎ)」について説明します。
巫(かんなぎ)とは?
巫(ふ、かんなぎ)は、巫覡(ふげき)とも呼ばれ、神に仕え、神の意志を人々に伝える役割を持つ人々を指します。女性は「巫」、男性は「覡」や「祝」と呼ばれます。「かんなぎ」という言葉は特に日本の巫を指します。
日本では古くから巫の多くは女性であり、「巫女(みこ、ふじょ)」と呼ばれることが一般的でした。つまり、巫=巫女と言えます。
巫は本来、「神降ろし」や「神懸り(かみがかり)」といった儀式を指します。古神道(日本に外来の宗教が入る前の原始宗教)では、神を鎮めるためのさまざまな行為の中で、特に祈祷師や神職などが依り代(神霊が依り憑く対象物)となり、神を自らの身体に宿す儀式が行われていました。これらの儀式を司る女性が巫と呼ばれていたと考えられています。
現代の巫女
現代において「巫女」という言葉は、神道の神職を補佐する女性のことを指すことが多いです。神社で神主の補佐をしたり、お守りを売ったりする巫女が一般的なイメージです。しかし、神降ろしのような儀式とは少し異なる印象があります。では、どのようにして現代の巫女像が形成されたのでしょうか?
巫女の2つの分類
巫女は「巫系巫女」と「口寄せ系巫女」の2つに分類されることがあります。この分類について説明しながら、現代の巫女像がどのように形成されたのかを整理していきたいと思います。
神を崇拝し仕える神社巫女と、霊を呼び寄せる役割を持つ巫女
神々への奉仕や、その意志を人間界に伝達する女性の存在に焦点を当ててきました。
柳田國男は、彼の著作『巫女考』において、日本の巫女を主に二つのグループに区分しています。
・神道の神社で勤める女性たち(神社での巫女)
・霊を自分の体に召し、神託や儀式を実施する女性たち
これらの区分に基づき、それぞれのグループについて探究していきましょう。
神社での巫女
このグループに属する女性は、神道の神々や霊を祀る儀式に関わります。
この役割を持つ女性は、時代を通じて徐々にその役割が変わってきました。
例えば、古代には卑弥呼がこのグループに含まれ
→当時はシャーマニズムの影響が強く、巫女の役割は重要でした
明治時代には、神職が男性に限られ、女性の神職が一時的に存在しなくなり
→巫女は儀式の補助者となりました
第二次世界大戦中に、女性神職が再び登場
→広義において、女性神職と儀式の補助者を巫女と称するようになりました
このように、巫女の役割は時代と共に変化してきました。
また、巫女が女性であることによるイメージの変化も見られます。
もともと巫女は「神子」とも称され、神の配偶者という意味合いがありました。古代日本では、皇族の未婚女性が斎王として神に仕え、結婚しないことが多いとされます。
この「神の配偶者」というイメージから、宗教儀式に性的な要素が加わることもありました。
しかし、日本に仏教が導入されると、巫女の性的なイメージは排除されました。
その一方で、「神の配偶者」というイメージは、処女性を重んじる方向へと変わりました。
女性性のイメージは以下のように進化してきました。
神子=神の配偶者
性的なイメージ
仏教導入による性的イメージの排除
逆に、神の配偶者としての処女性が強調
巫女=神社という神聖な場所の象徴へ
現代では、このような背景から、若い女性が巫女となる傾向がありますが、結婚を機に退職することが多いようです。
霊を呼び寄せる役割の巫女
このグループの巫女は、自分に霊を憑依させたり、死者と生者の間を繋ぐ役割を担ったりします。
特に知られているのは、青森県のイタコや沖縄のユタなどです。
このタイプの巫女は、多くの場合、家系によって技と資質が受け継がれます。中には、成長してから神託を受け、憑依の才能を開花させる女性もいます。このような巫女は、シャーマンとも呼ばれます。
巫女は
狭義での意味では神社での巫女
広義での意味では霊を呼び寄せる巫女、つまりシャーマン
として理解することができます。
続けて、各地のシャーマンや巫女についての探究を続けます。
各地域のシャーマン・巫女について
これまで、巫女について説明してきましたが、巫系巫女(現代の巫女に該当)と口寄せ系巫女(シャーマン)が存在することを述べました。
ここからは、日本各地のシャーマン(巫女)の具体例を見ていきましょう。
《東北》イタコ、カミサマ
まずは東北地方のシャーマン・巫女について紹介します。
≪イタコ≫
イタコは青森の恐山で知られる口寄せ系巫女です。以下の特徴があります。
- 死者の霊を呼び寄せる
- 霊媒的な要素が強い盲目の巫女
- 視覚障害を持つ女性がなる
- 死者降ろしを行う
≪カミサマ≫
次にカミサマは、青森県津軽地方で信仰される口寄せ系巫女です。
- 独自の霊感や神霊体験を持つ一世代限りの巫女
- 守護神との対話を通じて相談者に助言
- 憑き物祓い
- 病気治療
- 神降ろし
イタコとカミサマは共に東北地方の口寄せ系巫女ですが、死者を呼ぶイタコと神と対話するカミサマとでは役割やアプローチが異なります。
次に、関東と京阪地方の巫女の呼び方について整理します。
《関東》ミコ、イチコ、アズサミコ
柳田國男によれば、同じ呼び方でも地域により異なる意味を持ちます。関東地方では、
- ミコ:巫系巫女
- イチコ・アズサミコ:口寄せ系巫女
《京阪》イチコ
関東とは異なり、京阪地方では、
- イチコ:巫系巫女
次に、沖縄地方の口寄せ系巫女について説明します。
《沖縄》ユタ、ノロ
ユタとノロは同じ口寄せ系巫女ですが、役割が異なります。
≪ユタ≫
ユタは一般人に霊的助言を行うシャーマンで、沖縄の日常生活に深く関わっています。
- 占い
- 先祖供養
- 災厄除去
- 病気平癒祈願
≪ノロ≫
ノロは村落の祭祀を司る女性祭祀者の長で、琉球神話の神々と交信します。かつては公的な巫女として制度化されていましたが、現在はその地位を失っています。
ユタとノロはそれぞれ異なる役割を持ち、沖縄のシャーマニズムを支えています。
【要約】日本のシャーマンについて
≪神社に関わる巫女≫
神道の儀式に参加する女性
元々はシャーマン的な役割を持っていたが、現在では神職を助ける女性として知られている
≪口寄せを行う巫女≫
神霊を自身に降ろし、死者との対話や神の力を行使する
典型的なシャーマンであり、例として恐山のイタコが有名
≪日本各地のシャーマン≫
東北地方 イタコ、カミサマ
関東地方 ミコ、イチコ、アズサミコ
関西地方 イチコ
沖縄地方 ユタ、ノロ
普段、神社で見かける巫女さんや、テレビなどで見たことがあるかもしれないイタコなどのシャーマン。この記事を通じて、なぜ同じく「巫女」と呼ばれるのか、そして両者の違いについて理解が深まったのではないでしょうか。